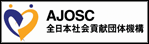遠野まごころネットの個人ボランティアとして、23日から遠野に滞在中の松下達也さん(49=会社員)は、神戸からやってきた。22日の夜に家を出て、夜行バスと電車を乗り継いで23日の朝に仙台に着いた。そのまま、周辺の被災地には目もくれず、人生で初めてのボランティア活動のため、縁もゆかりもなかった岩手の地に乗り込んだ。「首都圏から近い宮城には、きっと大勢の人が入ってるやろと思って。それに(民俗学の権威)柳田国男の故郷の兵庫県民やから(柳田の著書「遠野物語」の舞台)遠野は、特別なあこがれがあったんですわ」と屈託なく話した。遠野入りした理由はもう1つあった。震災のあと、雨後のたけのこのように誕生したボランティア組織の中から、妻の智子さん(45)がインターネットで、遠方からの個人での参加を受け入れている遠野まごころネットを見つけてくれた。ほかにもいくつかあった候補の中で、おそるおそる最初にかけたまごころへの電話。応対した女性スタッフから「歓迎します!ありがとうございます!」と言われて即決した。
被災者の気持ちは誰よりも分かっている。今から16年前の1995年(平7)1月17日、松下さんは阪神淡路大震災で、親戚3人を亡くした。自身も自宅が半壊し、妻と当時2歳だった一人息子とともに、長田区の小学校の体育館で1カ月半、避難民として暮らした。「自分の人生がどうなってしまうのかわからない孤独感と不安。そして、どこにも持って行きようのない怒り…。そんな絶望的な状況で、続々と救援に駆けつけてくれた自衛隊や警察官、そして全国からのボランティアのみなさんの姿が、涙が出るほど心強かった。だから、今回、何が何でもその時のお返しをしたかったんですわ」。勤務先の須磨区生まれの社長が朝礼で「被災地に行く気のあるヤツは行ってこい」と訓辞した時、真っ先に手を上げた。「他のボランティアさんはみんな『微力ですが、少しでも…』と言いますよね。でも、おこがましいかもしれませんが、僕は『自分が来たからには大丈夫ですよ』と言えるぐらいのつもりで来たんです」と言い切った。 長期にわたる避難所生活の苦労は、今も鮮明に覚えている。震災当初の感謝も感激もやがて薄れ、誰もが心身ともに疲れ果てた。トイレの汚れ、配給の順番…住民同士が些細なことでも衝突し、けんかが絶えなかった。炊き出しの列に自分たちと一緒に並ぶボランティアたちの姿に無性に腹が立った。「普通なら『ありがとう。一緒に食べてってや』と思うはず。でも『あんたたちは家に帰れば、おいしいゴハンが待っているでしょう?』という気持ちになっていたんです。きっと今回もそうだと思う」。倒壊した家屋をバックに記念写真を撮るボランティアが許せなかった。失意に打ちのめされ、すさんだ被災者の心情は。経験したものしか分からないと信じている。
前日25日には大槌町に行き、床上浸水した住居の家具搬出、床下にたまった泥の撤去作業に従事した。一緒に働いたボランティアたちがまったく無意識に、転がっている瓦礫に腰掛けて昼食をとるのを見て、胸が張り裂ける思いだった。彼らが移動中に、以前は花壇だったと思われる石垣の中に足を踏み入れ、むき出しになっていた球根を踏んだ時、ついにたまりかねて注意した。「壊れた石垣も、落ちているフェンスもごみじゃないんだよ。ヘドロで埋まった庭も、落ちている汚れたボールだって、住んでいた人には歴史の詰まった大事なものなんだよ」と。
29日まで遠野に滞在する。できれば、避難所を訪れて、かつての自分と同じ境遇の人々を励ましたい。そして、ボランティアを志す全国の人たちには、配慮を欠いた何気ない行動が、被災者の心の傷に塩を塗ることもあるのだということを「1人でも多くの人に知ってほしい」。心からそう願っている。