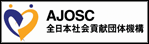たとえ津波をかぶっても個人の記憶の引き出しのなかにふるさとは生きている。漁から帰ってきた船のエンジンの音、見慣れた海辺の風景、魚の匂い、おばちゃんたちのにぎやかな笑い声、毎日何げなく食べていた旬の刺身や熱々の味噌汁・・・浜での暮らしはすべてが五感につながっている。海とともに生きてきた三陸沿岸部の人々にとって、毎日の食卓に魚料理が並ばない日などなかった。水揚げされる魚で四季の移り変わりを感じ、とれたてを地元ならではの調理法で食べ、台所から出た魚の生ごみは再び海に戻す。浜の暮らしでこれはごく当たり前のことで、生産と加工の現場、そしてそれを支える地元の人々の食卓は豊かな海と共存しながらひとつの環を形成していた。
しかし、海から切り離された場所にある避難所や仮設住宅の生活ではそうはいかない。実際にこれまで仮設住宅を訪問した際にも、「台所のスペースが手狭で、魚がさばけない」、「IHコンロ(クッキングヒーター)は使い慣れないので、うまく魚を焼くことができない」、「やっぱり焼魚が食べたいので、魚焼き用のロースターを買った」などと話される方がいらっしゃった。仮設暮らしでは魚を調理した後の生ごみの処理に困るという切実な声もある。3.11を境に三陸の魚介類が食卓から姿を消し、新鮮な魚を食べる機会が激減したことに多くの人が心を痛めていた。
このなかで、地元でとれた魚をおなかいっぱい食べて少しでも元気になってもらいたいという願いを込めた「秋の味覚祭」が10月にみんなの仲良し広場で開催され、私もお手伝いとして参加させて頂いた。秋の味覚といえば誰もがサンマを連想するだろう。大船渡は日本でも屈指のサンマの水揚げ量を誇り、地元の人々にとってサンマは日常生活と密着したふるさとを代表する魚のひとつだ。しかし、今年は津波で三陸の水産業が壊滅的な打撃を受けたため、しばらくは大船渡のサンマを味わうことも難しいのではないかと漁業の継続が危ぶまれていた。だからこそ、今年の秋に三陸の海でとれたサンマを食べるということは、地元の人たちにとって漁業の再生や失われた日常を取り戻す過程で大きな意味を持っていた。
大船渡エリアを中心にボランティア活動を続けている佐藤祐治さんは、「避難所で出会ったある女性から魚が食べたいのに食べられない、魚を食べたいと言われたことがこの企画を考えたきっかけだった」と話す。この佐藤さんの熱意に共感した片山和一良さんはみんなの仲良し広場を活用することに快諾。そして、三陸とれたて市場の八木健一郎さんが提供してくださった地元の新鮮な食材を使って、郷土料理のベテランである浜のお母さんたちが「サンマのつみれ汁」や「イカのふぞから」を作ってくださった。越喜来の復興に向けて地道に取り組む地元のみなさんや、全国からやってきたボランティアの想いがひとつに結集できた心温まるイベントとなり、秋晴れの空のもとで輝いていたたくさんの笑顔が今でも忘れられない。
津波の甚大な被害を受けた越喜来地区で、まさかこんなに早く地元の海でとれたサンマを食べることができる日が来るとは思わなかった。地元で普段から食べ慣れたものが再び食卓にのぼることは、失われかけていた心の拠り所をまたひとつ取り戻すことでもある。その土地でとれた食べ物をその土地の風土に合った方法で食べることが最も体に良いとする考え方を“身土不二”という。ふるさとを大切に思う人々が守り続けてきた地元ならではの味は、何よりも心や体に生きるパワーをもたらしてくれるものだろう。
お孫さんと一緒に参加されたある年配の女性は「今日は本当に来て良かった。この子は魚が大好きなのに震災後は魚を食べる機会が本当に少なくなってしまってね・・・今日だけはおなかいっぱいお魚を食べてもいい?と楽しみにしていたのよ」とおっしゃっていた。お孫さんは大きなサンマを2尾もペロリとたいらげて、とても満足そうだった。
この女性はお孫さんたちと同居しているそうだが、実は3.11以降、「津波のショックや放射能に対する不安から娘が孫に魚を食べさせたがらなかった」という。娘さんは3月11日に配達の仕事で陸前高田市に出かけていて地震に遭遇。帰宅途中の高台で津波が陸前高田の町を襲う場面を目撃してしまったそうだ。「娘はたった20分前まで自分もあの町でお客さんと仲良くしゃべっていたのに、町がまるごと海に消えたのを見て、なかなかショックから立ち直れないようです。あまり笑わなくなってしまって・・・」。坊やが嬉しそうにサンマを食べていた理由がわかった私は何と答えたらよいのかわからず、ただ、話を聞くことしかできなかった。
たとえ自宅が流失や全半壊から免れても、家族が無事だったとしても、津波はさまざまな形で人々の心に多くの見えない傷を残している。本人でなければわからない悲しみや苦しみもあるだろう。魚が食べたいのに物理的な理由からこれまでのように頻繁に魚を食べられないストレスを感じる人々がいる一方で、放射能汚染への懸念や、たくさんの身近な人が海に呑みこまれてしまった衝撃から心理的に魚を食べられなくなったというストレスを抱える人がいるのも悲しい現実だ。私の目の前でぱくぱくとサンマをほおばっていた坊やはどれだけお母さんのことを気遣い、心を痛めていたのだろうか。食べ終わった坊やが「おさかなおいしかったよ。きょうはおおきいのをふたつたべた」と笑顔で話してくれた時、このイベントに託されたみんなの願いや想いはこの坊やの心にもつながっていたのだと感じた。
みんなの仲良し広場に集まった地元の方々は、お茶を飲みながらいろいろなことを語り合っていた。「今までは建物があって気づかなかったけど、何もかもなくなってみるとこの場所はこんなに海から近かったんだね」。みんなの仲良し広場は海抜15メートルという。「本当に津波が来るまではすべて当たり前の暮らしだと思っていたよ」、「こうやって仮設住宅の外でみんなが集まる機会があるとありがたい」―――
7~8月頃から各地の仮設住宅では、入居者どうしの交流や新たなコミュニティづくりを促すことを目的としてお茶っこ会などさまざまな催しが開かれている。しかし、在宅避難をしている人や民間の賃貸住宅(みなし仮設)で暮らす人たちはこのなかに入れてもらうことができない。震災直後から生活情報の伝達や支援物資の配布、心のケアなどさまざまな面で在宅避難者やみなし仮設で暮らす人たちのフォローは置き去りとなりがちの状況が続いていて、被災地では自助努力の限界や孤立化を懸念する声も少なくない。9ヵ月前までは仮設住宅で暮らす人たちも仮設以外で暮らす人たちも、同じ地域に根付いたコミュニティのなかでともに生活を営んでいた。3.11以降の日々を必死で生き抜いてお互いが今、ここにいるわけで、それぞれの家庭の事情や暮らす場所の形態の違いなどによって支援の格差や不要な垣根が生じるようなことがあってはならないと思う。仮設で暮らす人たちも仮設以外の場所に暮らす人たちも、お互いに住民どうしの交流や情報交換、心の拠り所となるような場所や機会を求めていることに変わりはなく、地域の方々が誰でも自由に参加できるような集いの場や、協働の場をいかにみんなで創出していくかが今後のふるさと再生の鍵を握っている。
(取材・文:高崎美智子)