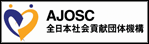復興支援検証会議ダイジェスト
~いま改めて、「支援」の原点を見つめ直す~
第1部:NPO・ボランティアの役割とその検証(3)
~(2)から続く~
―――吉田 信雄氏(かながわ県民活動サポートセンター)
神奈川県も静岡県のまごころ寮を参考として、昨年7月に「金太郎ハウス」という岩手にボランティアに行く方々のための宿泊拠点を設置した。
今回の会議では、僕たちがやらなければならないアクションについての提言と、機能しなかった課題について話をしたい。まずは災害ボランティアという言葉をきちんと定義しなければならないと思う。冒頭の栗田さんのお話のなかで、災害救援ボランティアの初動が遅れたという反省をされていた。僕もその通りだと思うし、海外での緊急支援の経験があるNGOなどがプロ市民として現地に入っていくことは重要だと理解している。一方で、その活動のすべてをボランティアと呼び、有象無象のボランティアが現地に行くことを歓迎するという意味ではない。災害救援ボランティアの初動体制を整えておく事が非常に大事だ。
地域でNPO支援をしている立場から言えば、避難所のなかで元気な人が元気のない人を応援するような個人対個人のボランタリーな活動がたくさんある。それを何かボランティアのような言葉で表現しないままでもよいのか。僕も震災以降、非常に多くの電話を頂いた。「神奈川県はボランティア支援をしないのか」など多くのお叱りを受けたが、僕はボランティアに行くことを止めたことは一度もない。「もしも(現地に)行くことが可能で、ご親戚やお友達が避難所にいるのがわかっているならば、何か物資を持っていくのもひとつのボランティアなので、ぜひ実行してください。難しいようであれば少しお待ちください」と答えていた。良いと思うことは実行すればよい。そういうことを行うボランティア活動が一番大事ではないか。神奈川大学の学生が現地に行った時、マンガが必要だと言われたので避難所の友人に「ONE PIECE」を送ったらとても喜ばれたそうだ。受験生には自分が使った赤本やノートを送り、勉強を教えるという。その話を聞いてこれこそボランティアだと思った。彼のセンスに感動した。このようなボランティアを定義する必要がある。
最後が災害ボランティアだ。水害など大きな被害のなかで、現地の方々の力になれる部分もたくさんある。一方で、(災害ボランティアの)支援機関は地元の方々とうまく連携しながら、ボランティアとしてかかわりたいという大勢の人たちを中央集権的にマネジメントしなければならないという側面もある。森本さんや僕から見ると、本当にそれをボランティアと呼んでいいのかという自問自答もある。これら3つの言葉(ボランティア)をある程度定義しておかなければ、常に災害ボランティアという漠然とした言葉のなかで、お互いの世界観をぶつけあっても仕方がない。その点は僕らに残された課題としてしっかりとしたフレームワークを持たなければならない。
問題なのは、被害が想像を超えた状態なのに既存のルールをあてはめようとすること。普段はこうやっているからこうしようとか、決まりだからとか。そういう場合ではないのに。ルーティンではないことが起きた時にどうするか。外部から来た人が現地のルールを良い方向に変えてもいつかは帰ってしまう。そこまで責任を負えるのか。外部の人はなかなかそこまで踏み込めない。このような(想像を超えた)状態が起きた場合、もはや元には戻らないので何か問題が起きても、より良くなるためのプロセスだと考える。既存のルールを乗り越えて頑張ろうとお互いに(気持ちを)シェアした時に初めて、現地の方のリーダーシップやビジョンを外部から来た人たちが支えるという関係ができる。外部と内部の関係性をお互いに理解しなければ、初動体制がうんぬんという話になってしまう。これは大きな問題だと思う。
行政や公共機関、NPO、NGOが協働することは難しい。状況の移り変わりが激しく、朝令暮改は当たり前なので情報の共有も難しい。(うまく協働するためには)常に現場を共有する以外に答えはないと感じる。石巻の会議(石巻災害復興支援協議会/石巻市災害ボランティアセンター)や遠野まごころネットがうまく機能した理由は、そういうマネジメントを心がけた点にあるのではないかと思う。
―――松永 秀樹氏(ジャパン・プラットフォーム)
ルーティンではないことが東北では起きた。そのような時、マニュアルもないなかでどう対応するか。我々は何らかの組織に属していると、その組織特有の既成概念やマニュアル、前例などにとらわれがちとなる。そうではなくて、いかに一人一人が(既成の枠組みを超えて)動けるか。吉田さんが最後にお話された石巻や遠野の話、それがパーフェクトではないが、そこに潜む要素は何だったのかということをもう少し議論していきたい。ここで、頼政さんにもお話を伺いたい。
―――頼政良太氏(被災地NGO協働センター)
私は震災後、日本財団ROADプロジェクトの事務局に出向し、足湯ボランティアの送り出しをしている。静岡県の図上訓練のネットワークや、阪神大震災以降に活動を続けてきた「震災がつなぐ全国ネットワーク(しんつな)」とも協働して活動しており、しんつなの各団体とも顔が見える関係ができていた。先に被災地に入ったしんつなの団体から東京にも情報が来ていたことで他の団体も安心してボランティアを送り出すことができた。災害前に顔がつながっていた関係があったのは大きいと思う。
―――会場からの声(岩手県北観光バス関連会社の関係者)
岩手県北観光と一緒に4月頃からボランティアバスを商業ベースでどんどん出した。地元のバス会社自身も被災しており、観光も打撃を受けていた状況だった。機能したものとしては、間口を広げることに役立てたのではないかと思う。個人がバラバラに入るよりもまとまって現地に入ってもらうことでボラセンにもお役に立てたのではないか。参加者もパッケージツアーになっていることで、参加しやすかったようだ。旅行会社が継続的なビジネスとしてボランティアやNPOと協働できたことはひとつの大きな成果だろう。機能しなかったものとしては、メディアに出てこない地域へのツアーをもっと重点的にやりたかったが、応募者が集まらなかったことだ。また、冬が近づくにつれてツアーの本数が限られてしまう。継続性の観点や、一部の地域に人が集まりがちであることなど旅行会社としてうまく提案できなかった部分もある。現地では社協のボラセンに(受け入れの)お願いをしていたが、もっと早い段階から遠野まごころネットや個別に動いている地元のNPO、例えば吉里吉里国などと結びついて動けばより効率的かつ、どのような活動があるのかを東京に伝えながらできたのではないかと思う。
―――臼澤良一氏(遠野まごころネット 大槌町)
想定外の被災のなかでは行政が全く機能しない。大槌の避難所で唯一、(支援に)来てくれたのは多田さんだった。行政に言っても全く役に立たないなかで、私たちは遠野まごころネットのお世話になった。さきほど頼政さんが「以前から顔がつながっていた」というお話をされていたが、どのような場面でどのように顔がつながったのかを具体的に聞きたい。
―――頼政良太氏(被災地NGO協働センター)
我々のネットワークで年に2回の会議をしていることや、静岡の図上訓練をみんなで行っていたことが大きかった。各団体のメンバーで災害時にはどうやって現地に入ったらよいのかを集まってとことん話し合う。長時間にわたり、一緒に何かを考えて本音を語りあうことで顔がつながり、他団体の動きなども想像がつくようになった。そういう議論をしていたのが良かったのではないかと思う。
―――臼澤良一氏(遠野まごころネット 大槌うすざわ広場)
「現地の顔が見える」とは、例えば大槌の支援団体と直接顔がつながっていれば想定外の被災があってももっと具体的な活動がスムーズにできたのではないかということ。身内のNPOやNGOのつながりではなく、被災前に(被災した)自治体と具体的なつながりがあったのかを聞きたい。
―――頼政良太氏(被災地NGO協働センター)
今回の震災前に東北地方と我々のネットワークの間につながりがあったかといえば、薄かったと思う。(レスキューストックヤードと七ヶ浜のように)もともとそういう関係があれば現地にもスムーズに入れるので、行政や地域の社協、外部のNGOやNPOと今回できたご縁を大切にしていきたいと思う。
―――鳥羽茂氏(静岡県ボランティア協会)
まごころネットは3月28日に活動を開始した。27日の午前中、遠野市社協で多田さんや荒川さん、菊池さん、社協の佐藤さん、被災地NGO協働センター代表の村井さんたちが会議をしていらっしゃるところに私はたまたま居合わせた。話合いのなかで多田さんはとにかく現地に行かなければという気持ちが強かった。遠野では市内に避難している方々への支援や炊き出しなどを行っていた時期だが、これから多くのボランティアがやってくる。とにかく被災地支援に向けた水先案内人を地元の人たちがしなければならない。多くのボランティアが全国から来る前に、まずは多田さんたちを中心に遠野の人たちが被災地に入ってつなぎをするということがとても重要な時期だった。我々には現地とのつながりがないので、なおさら地元や周辺の方々がつながりを作ることが大事だった。
―――山口幸夫氏(日本社会事業大学)
今の考え方は中長期に向けた(現地の)混乱に象徴されると思う。緊急救命期には医療や物資、毛布、マンパワーなどをある程度外部からどんどん持って入ってこなければならないが、そこから先(の時期をどうするか)。遠野まごころネットや七ヶ浜の場合、なぜ現場が混乱しないかといえば、地域の人たちが自分たちの人的なネットワークやいろいろなものを動員しながら、自分たちのニーズをクライアントとして語り、それをみなさんでサポートして下さいというスタンスだからだ。そのような状態に早く持っていかなければならない。
発展途上国(における活動)でもよく起こることだが、大手の支援団体が入ってくると最初は助かるが、時間が経つにつれて「こうしてください、ああしてください」と自分たちが顧問になって仕切ろうとする。このパターンになると現地は混乱してしまう。クライアントは被災者だ。まごころネットができたのは3月下旬だが、例えば大槌の臼澤さんにはすでに3/14頃に物資を持ってきていた。多田さんたちが現地に飛び込んだ時、地元の社協にはまともな地図がなく、自衛隊も持っていなかった。現地でそういうレジスタンス的な活動に取り組んでいる人たちを水先案内人と見るのか、それとも地域の人たちが戦っているからそのサポートのために我々は行くのか。外部の支援者が入って自己主張をすると混乱を招くことになる。我々はサポートをするために入っていくべきだ。被災された人たちの気持ちや各地域のコミュニティをどうするかということをきちんと考えなければならない。
―――会場からの声(ジャムズネット東京)
ミスマッチというものがかなりあると感じた。ボランティアをする側、社協、ボラセンなどの立場については良く理解できたが、今の話を聞いてクライアント側、(支援を)受ける側のミスマッチの部分をもう少し議論すべきではないかと思う。東北の方の気質もあるだろうが、ボランティアをする側と受ける側とのミスマッチのギャップがある。私たちはこれが必要だからではなく、支援を受ける側になった時に本当にこれでいいのかという部分の検証が必要ではないかと思う。ここに来ている人を見ると、どちらかといえばボランティアをする側の人たちばかりが集まっているようなので、支援される側での物の見方も議論に加えたほうが良いと思う。
―――松永 秀樹氏(ジャパン・プラットフォーム)
第2部につながる話だが、支援する側の自己満足になってないかを常に考える必要がある。現地の状況は時間経過とともにものすごい速さで変化していく。神戸での経験が福島や岩手、宮城にすべてあてはまるわけではない。また、これまでの議論は岩手や宮城の話であり、福島になると状況が全然違う。福島への支援は本当に少ない。私自身も福島の支援に入ったのは昨年11月だったが、全く状況が違うので唖然とした。時間や場所によって状況が変わる一方で、支援者側はどうしても自己満足に陥りがちだ。そこが現地とのミスマッチが生じる原因になっているのではないか。ここで、福島県浪江町の原田雄一さんにもお話を伺いたい。
―――原田雄一氏(まちづくりNPO新町なみえ)
やはり浪江町の状況は他の地域の方と全く違う。私たちはコミュニティを完全に壊され、避難させられたことが一番異なる点だ。浪江も海岸線から約2キロのところまで津波がきて、100数人が亡くなられた。まさかこんな津波が来るとは思わなかった。(海辺を)見に行って亡くなった方もいた。チリ地震津波の時、浪江はかなり遠くまで潮が引いたが、波は堤防を越えなかったことがお年寄りの記憶にあったので、海岸線からかなり内陸に入った場所でも亡くなられた方がいた。浪江は放射能の問題で危ないから入れないという事情もあって、私たちに(ボランティアを)受け入れるという議論はなかった。ただ、これまで多くのみなさんからご支援を頂いたことは、一町民として本当に有難いと感謝している。
―――松永 秀樹氏(ジャパン・プラットフォーム)
現場の状況は場所や県のくくりでも違う。支援者側はいかに現場を把握しながらニーズに応じたきめ細かい支援をできるか。支援者側の我々の姿勢はどうしてもボランティアやNPOは良いことだと思い込みがちだ。そこにとどまらず、変化するものに対してきちんとニーズを満たすことができているのか、第2部で議論していきたい。
―――多田 一彦氏(遠野まごころネット)
後半につながる課題をみなさんから一言ずつ挙げてもらえないだろうか。
―――吉田 信雄氏(かながわ県民活動サポートセンター)
災害ボランティアという言葉のなかで消されてしまう、避難所などで起きていた助け合い、もしかしたら中学生がお年寄りを救いながら生きていたような話と、いわゆる災害ボランティアと呼ばれるものは分けるべきだと思う。災害ボランティアと呼ばれる活動については、難しい部分も多いので慎み深い感覚が必要だ。仮に災害ボランティアというものから今後の災害につながる何らかの経験を学ぶ側面が強かったとするならば、このフィードバックはどうなるのかという問いを常に支援者側が持たなければならない。「現地に行きました、風化させてはいけません、努力します」で終わっていいのか、そのあとのサイクルをどうするのか。それぞれの地域に戻ってこの風化をどう止めていくかを考えた時に支援団体はきちんとしたビジョンを持たなければならないし、単に片棒を担いだだけでは済まされない。その部分は僕自身にとっても大きな課題だと思う。
―――鳥羽茂氏(静岡県ボランティア協会)
(震災から)一年経ってはじめて言える、話せることがいっぱいあると思う。今、本当に辛くなっている状況が被災地のなかにたくさんある。もっとそういう部分に近いところで話を聞いて一緒に考える、一人一人が距離を縮める努力、これからもかかわっていくことが必要。静岡県としても現地と細く長くかかわり続けることが大事だと思う。
―――頼政良太氏(被災地NGO協働センター)
ひとつひとつの仮設住宅や避難所によって全然状況が違う。ここの避難所では炊き出しがあるのに、別の避難所ではおにぎりだけということがあったように、仮設住宅でもいろいろな差が出ている。ボランティアが頻繁に来る仮設と来ない仮設、自治会長さんがいる仮設といない仮設など、その場所によって課題が少しずつ違ってきている。被災地共通の課題から、日常生活につながる個々の課題にどんどん変わっていくのだろう。今までのようにボランティアが全員同じことをやればよいということではなく、それぞれのボランティアが行く場所に応じてどのような役割やサポートができるのかをもっとしっかりと考えていかなければならない。震災関連死などの問題もこれから深刻になる可能性があるので、いろいろな形のボランティアをいろいろな人たちでやることが重要だということをもっと発信していくべきだ。
―――森本智喜氏(全社協支援P)
課題は姿勢と立ち位置だと思う。被災者主体という言葉がある。被災していくらいろいろなものを失っても、やはり自分のことは自分でやりたい。自分たちの町は自分たちで新たに創っていきたい。それが今、思うようにできない状況にある。初期の段階でなぜおにぎりや服を届けたのか? 地元の人たちは(おにぎりを食べて)お腹がいっぱいになれば自分の家を片付けてみようか、(服を)着込んで暖かくなれば少し体を動かしてみようかという気持ちになる。我々はそのお手伝いだ。被災した地元の人達の意欲を支えるため、意欲を生むエネルギーを強くするために我々は支援をしてきたのではないか。
もうひとつ、僕は災害ボランティアとか、災害ボランティア活動というと結局よくわからなくなってしまう。そうではなく、誰のため、何のためにすることなのかをはっきりさせるために我々の活動は「被災者支援活動」だと陸前高田で言い続けてきた。なかには指導や指示をしたがる人や無意識のうちにしている人も見受けられた。このことが地元の人たちを傷つけたり、嫌気がさすような状況をつくる場面もあった。フェーズを進めるのも地元の人たちで、どのような町にしていきたいかを考えるのも地元の人たちだ。自分たちは誰のために来ているのか、何のためにいるのか、支え助ける人としての姿勢と立ち位置を見失わずにこれから先も長い年月にわたってかかわり続けていくことが課題だと思う。
~第1部おわり~
(まとめ・文:高崎美智子)
関連するエントリー
復興支援検証会議:第一部